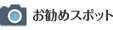お台場の歴史~成り立ち~公園として残る国指定の史跡

東京屈指の観光スポットのお台場。
この地域の埋め立て事業は、港区の地先は明治時代に、品川区の地先は大正時代に始まり、戦前にはほぼ完成していましたが、大田区の地先は遅れて始まり、戦後になって埋め立てが完了しました。
開発が始まったのは数十年前のこと。現在のお台場に至る歴史を見ていこう。
この地域の埋め立て事業は、港区の地先は明治時代に、品川区の地先は大正時代に始まり、戦前にはほぼ完成していましたが、大田区の地先は遅れて始まり、戦後になって埋め立てが完了しました。
開発が始まったのは数十年前のこと。現在のお台場に至る歴史を見ていこう。

~品川沖での潮干狩りの様子~
かつては品川沖という海だったお台場
先述の通り、お台場は埋め立てられてできた街。
数百年前は品川沖とよばれる海でした。
日本では物資を輸送する手段として広く船が使用されていました。
品川沖は物流の拠点として大型の貨物船が停泊し、小型の船に荷を積みかえて江戸に運んでいたのです。
寿司には欠かせない「海苔」の原料となる海藻の産地としても知られています。
有名な浮世絵には、潮干狩りをする様子が描かれており、界隈は賑やかな港町であったことがわかる。

~黒船~
日本を揺るがした歴史的事件~ペリー来航~
1639年から1854年まで、交易の窓口だった出島(現在の長崎県の一部)を除き、外国人の入国を禁じる法律がありました。
1853年にアメリカ大統領の親書を携え、神奈川県の浦賀沖に開国を要求する四隻の軍艦がやってきます。
来航した神奈川県の浦賀沖から江戸に迫る勢いだった使節団に、日本は1年の猶予を求めて追い返す。
脅威を感じた幕府は、江戸の直接防衛のために海防の建議書を提出した伊豆韮山代官の江川英龍に命じて、洋式の海上砲台を建設させました。

~品川台場に設置されていた80ポンド青銅製カノン砲(遊就館蔵)~
お台場という地名の由来
品川沖に11基ないし12基の台場を一定の間隔で築造する計画でスタート。
工事は急ピッチで進められ、約5,000人が動員され8か月の工期で1854年にペリーが2度目の来航をするまでに砲台の一部は完成。
品川台場(品海砲台)と呼ばれました。
お台場という呼び方は、幕府に敬意を払って台場に「御」をつけ、御台場と称したことに由来しています。
年表:成り立ち~開国まで
| ~1853年(嘉永6年) | 品川沖として江戸の物流の拠点として栄える。近海では海苔の産地としても有名。 |
|---|---|
| 1853年(嘉永6年)6月 | アメリカからペリーが来航し開国を要求。 |
| 1853年(嘉永6年)7月 | 江川太郎左衛門英龍が品川沖に11基の台場を設計 |
| 1853年(嘉永6年)8月 | 第一から第三台場の建設開始 |
| 1854年(嘉永7年)1月 | ペリーが軍艦7隻を率いて再び浦賀に来航 |
| 1854年(嘉永7年)4月 | 第一から第三台場完成 |
| 1854年(嘉永7年)5月 | 幕府、第四・七台場の建設を中止(両方とも未完成) |
| 1854年(嘉永7年)12月 | 第五・六台場完成 |